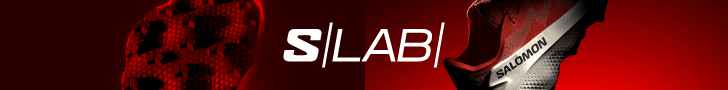スポーツ庁より「夏山登山の事故防止について(通知)」が発出されました。本格的な夏山シーズンが到来し、雄大な自然の中でのトレイルランニングは格別の魅力があります。しかし、その一方で、夏山では毎年多くの遭難事故が発生しているのも事実です。特にトレイルランナーは、その機動性の高さから、装備や計画が不十分になりがちです。安全に夏山を楽しむために、最新の遭難統計と具体的な対策を深く理解し、万全の準備をしましょう。

夏山遭難事故の現状と危険因子
2024年の山岳遭難は全国で2,946件発生し、3,357人が遭難しています。このうち、死者・行方不明者は300人に上ります。過去10年間で見ると、2020年から3年連続で増加傾向にありましたが、2024年は前年比で減少しました。しかし、依然として高い水準で推移しており、油断は禁物です。
特に遭難件数が多い都道府県は、長野県(321件)、北海道(189件)、東京都(183件)、神奈川県(183件)となっています。また、富士山や高尾山といった観光地としても有名な山岳での遭難者が増加傾向にあります。
主な遭難原因と年齢層: 遭難者の約8割が40歳以上で、そのうち半数が60歳以上と高齢層での事故が際立っています。 死者・行方不明者に至っては、40歳以上が91.7%、60歳以上が64.0%を占めています。
遭難態様別では、以下の3つが主要な原因となっています。
・道迷い: 30.4%
・転倒: 20.0%
・滑落: 17.2%
これらは、登山コースの事前学習不足、地図・コンパスの不携帯、地図読みスキルの不足、あるいは「つまずき」や「スリップ」による負傷が主な原因です。山中での重傷は自力での下山を困難にするため、一歩一歩慎重に行動することが求められます。
また、単独登山者の死者・行方不明者の割合は13.7%と、複数登山者(5.9%)と比較して約2.3倍も高くなっています。これはトラブル発生時の対処の難しさを示唆しており、原則として複数人での登山が推奨されます。 外国人観光客の遭難者数も、2023年に次いで過去2番目に多い135人(死者・行方不明者7人)を記録しています。
トレイルランナーが徹底すべき安全対策
1. 的確な登山計画と万全な装備の準備
- 計画の練り込み: ・自身の体力、技術、経験、体調に見合った山やコースを選びましょう。
・余裕を持った行動日程を組み、滑落の危険箇所やエスケープルート(万一の時の下山ルート)を事前に把握しておくことが重要です。・特に夏山は積乱雲の影響で昼前後から天気が崩れやすい傾向にあるため、「早発ち、早着き」を基本とし、夕立が降る前に安全な場所へ到着する計画を立てましょう。 - 装備の徹底:
- 必須装備(○): ・ロングパンツ、長袖シャツ、登山用靴下(予備含む)、登山靴、帽子、手袋(予備含む)、フリース等の防寒着、レインウェア上下、サングラス。
・行動食(塩分やブドウ糖含む)、飲料水・保温ボトル。
・時計(高度計機能付き)、スマートフォン(GPS機能付き、予備バッテリー必須)、バックパック、コンパス、1/25000地形図(紙)、登山専用地図、ルート図、登山計画書(緊急連絡先含む)、身分証明書、健康保険証、レスキューシート。
・筆記具、携帯トイレ、トイレットペーパー、タオル、ヘッドライト(予備バッテリー含む)、テーピング、ナイフ(マルチツール)、ホイッスル、熊鈴、ファーストエイドキット、日焼け止め。 - 状況に応じて持参(△): ・捜索用発信機(小型ビーコン)、ハンディGPS端末、カメラ、マット、ストック、テント一式、スタッフバッグ、シュラフ、シュラフカバー、ヘルメット、ハーネス、ロープ、カラビナ各種、スリング各種、スパッツ、ツェルト、ポリ袋(防水・ゴミ入れ等)、クッカー(調理器具)、ストーブ(燃料含む)、ライター・マッチ、ラジオ(予備電池含む)。・GPS機能付きの携帯電話は、現在地を救助機関に伝える有効な手段ですが、山岳地帯では電波が入りにくい場所も多く、バッテリー消費も早いため、予備バッテリーは必ず持参しましょう。
- 必須装備(○): ・ロングパンツ、長袖シャツ、登山用靴下(予備含む)、登山靴、帽子、手袋(予備含む)、フリース等の防寒着、レインウェア上下、サングラス。
2. 登山計画書・登山届の提出は「命綱」
- 登山計画書は、安全登山のための自己点検の機会となるだけでなく、万一の遭難時に迅速な捜索救助活動に繋がる「命綱」です。
- 家族や職場と共有するほか、以下の方法で必ず提出しましょう。
- 登山口の登山届ポスト
- インターネットの登山計画提出ウェブサイト・アプリ(例: コンパス)
- 山域を管轄する警察本部または警察署(ウェブサイト申請可能な場合もあり)
- 下山時も忘れずに下山報告(下山届の提出)を行ってください。
3. 最新の気象情報と火山情報の把握
- 山の天気は平地と比較にならないほど急変します。特に夏場は、発達した積乱雲の影響で急な大雨、落雷、突風等が発生しやすいため、入山する数日前から最新の気象情報を確認し、危険が予想される日は登山を控える勇気も必要です。
- 気象情報の入手先:
- 気象庁ホームページ:警報・注意報、キキクル(危険度分布)、天気予報、地上・高層天気図、気象衛星、アメダス、気象レーダーなど多岐にわたる情報が確認できます。
- 国土交通省防災情報提供センターホームページ:河川、道路、気象等の各種防災情報を見ることができます。携帯端末向けのページもあります。
- 民間気象会社も特定の山を対象とした気象情報提供サービスを行っています。
- 火山情報にも注意:
- 火山には噴気や火山ガスが発生している危険な場所があります。
- 気象庁の「火山登山者向けの情報提供ページ」で、噴火警報や火山の状況に関する解説情報を確認しましょう。
- 噴火速報は、ラジオやテレビのほか、スマートフォンのアプリでも知ることができます。「噴火速報について」も参照してください。
4. 道迷い・転倒・滑落防止と的確な状況判断
- 道迷い防止: 紙の登山地図とスマートフォン用の登山地図アプリを併用し、常に現在地を確認する習慣をつけましょう。 山岳地帯は電波が入りづらいこともあるため、事前にアプリの作動確認と予備バッテリーの持参を忘れずに。
- 転倒・滑落防止: 日頃から手入れされた登山靴を使用し、ストックなどの装備を適切に使いこなしましょう。 転落・滑落や落石の危険がある場所では、必ずヘルメットを着用してください。「ヘルメットさえかぶっていれば…」という悲しい事故も発生しています。
- 的確な状況判断: 霧(ガス)や視界不良、体調不良時には道に迷ったり冷静さを失ったりする危険が高まります。「道に迷ったかも」と感じたら、闇雲に進まず、来た道を戻るなど冷静に判断し、早めに登山を中止する勇気を持ちましょう。
5. 体調管理と水分補給
- 登山は体に大きな負担がかかります。体力消耗だけでなく、標高による低酸素、汗による脱水、ストレスなど、目に見えない負荷がかかります。
- 水分補給の目安: 体重(kg) × 行動時間(時間) × 5 (ml)
- 常用薬がある場合は必ず持参し、自身の体調と相談しながら無理のない計画と行動を心がけてください。
■スポーツ庁「夏山登山の事故防止について(通知)」